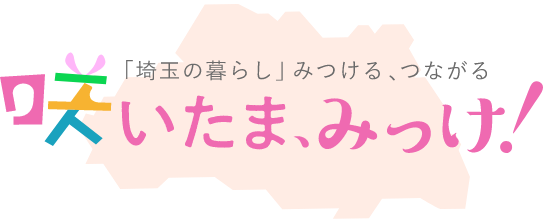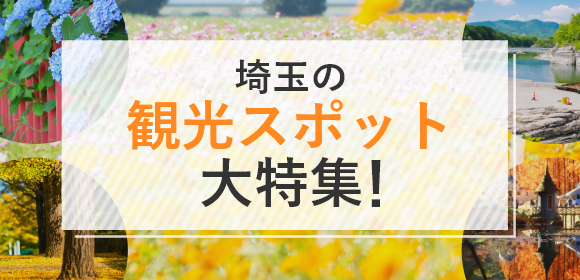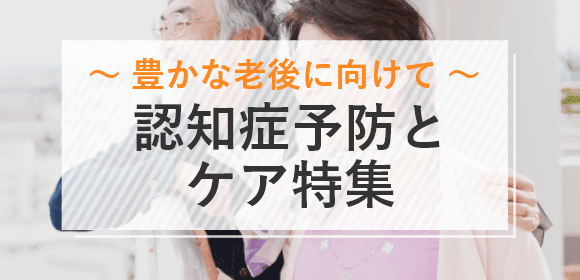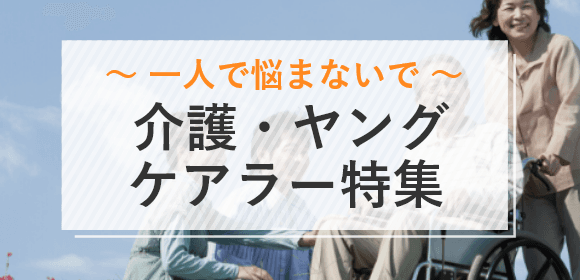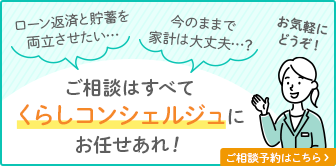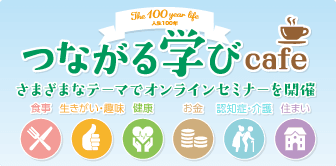睡眠の質を上げるには?
質が下がる原因や良い睡眠を取るための方法を紹介


「ぐっすり眠れない」「夜中に何度も起きてしまう」「寝ているはずなのに、疲れが取れない」など、睡眠の悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
睡眠は、健康を維持するために必要不可欠なものです。ただし、睡眠の「時間」だけでなく、疲れがきちんと取れるようにその「質」にも注意を払う必要があります。
この記事では、睡眠、特に睡眠の質についてさまざまな角度から解説します。ぜひ参考にしていただき、眠りの質を高めて日々の健康につなげてください。

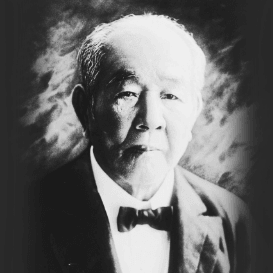
INDEX
睡眠時間と
睡眠の質について
厚生労働省が公表した『健康づくりのための睡眠ガイド2023』(外部サイトへのリンク)によれば、「良い睡眠は、睡眠の量(睡眠時間)と質(睡眠休養感)が十分に確保されていることで担保される」とされています。
特に、睡眠休養感=睡眠で休養が取れているという感覚は、睡眠の質を反映する指標といえます。横になっている時間が長くても、寝付きが悪かったり、夜中に何度も起きてしまったりするなら、質の良い睡眠とはいえないでしょう。
睡眠について、時間と質の観点から見ていきましょう。
必要な睡眠時間は年齢や季節で変化
睡眠時間には個人差があります。夜間に眠る時間は加齢によって徐々に短くなるため、必要な睡眠時間は年齢によっても変わってきます。前述の『健康づくりのための睡眠ガイド2023』によれば、小学生は9~12時間、中学・高校生は8~10時間、成人は6時間以上の睡眠時間の確保を推奨しています。
高齢者は特に睡眠時間が示されていませんが、長時間寝床にいることが健康リスクとなるため、床上時間が8時間以上にならないことが目安として示されています。
また、必要な睡眠時間は季節によっても変化します。冬は夏より10〜40分程度、睡眠時間が長くなるようです。冬は日の出ている時間が短いこと、逆に夏は日が長く、さらに高温多湿な寝室環境が原因になっていると考えられます。
睡眠の質を表す「睡眠休養感」の低下は健康にも影響する
睡眠休養感とは、朝起きた時に「睡眠で休養が取れた」という感覚を表すもので、睡眠の質の指標になります。目覚めた時に、「ぐっすり眠れた」「良く休めた」と感じられるなら、睡眠休養感が高いといえるでしょう。
睡眠休養感と健康状態には相関関係があることが分かっています。睡眠休養感の高さが、心筋梗塞、狭心症などの心血管疾患の発症率低下と関連しており、若年成人と女性ではこの関連が顕著であることが研究結果で示されています。
一方で、睡眠休養感の低下は、肥満や糖尿病、脂質異常症を含めた代謝機能障害と関連することも分かっています。また、65歳以上の高齢世代では、床上時間が長く(8時間以上)、かつ睡眠休養感が欠如している場合に死亡リスクが増加するという研究結果があります。
また、睡眠休養感は心の健康にも影響し、睡眠休養感が低い人ほど抑うつの度合いが強いという研究結果があります。
睡眠の質が低下する
原因はさまざま
睡眠の質が低下する原因はさまざまです。主に以下のようなものがあります。
- ストレス
- 仕事の悩みや家庭の心配事などのストレスがあると、交感神経が優位な状態になり、眠りが浅くなって睡眠の質が下がることがあります。
- 生活リズムの乱れ
- 床に就く時間が毎日大きく違うなど、生活のリズムがバラバラだと体内時計が乱れ、快眠が得られにくくなります。
- 睡眠環境が整っていない
- 寝室の温度や湿度が適切ではない、騒音があるなど睡眠環境が良くないと、睡眠の質が下がることがあります。
- 病気
- 不眠症、閉塞性睡眠時無呼吸、周期性四肢運動障害などの疾患が、睡眠の質の低下に影響することがあります。
睡眠の質の向上は、
生活習慣や就寝環境の
改善が鍵
睡眠の質を向上する方法はいろいろあります。日常生活の工夫や心がけで改善できますので、ぜひ取り入れてみましょう。
- 規則正しい生活をする
-
起床や就寝の時間が毎日決まっていると、体内時計が整い、睡眠の質が上がります。また、朝日を浴びることや朝食を取ること、日中にできるだけ日光にあたることも体内時計の調整に良い影響を与えます。また、寝る直前の夜食は体内時計に悪影響を与えることも分かっています。
体内時計は睡眠のタイミングを決定するだけでなく、前もってホルモンの分泌や生理的な活動を調節して、睡眠に備える働きがあります。規則正しい生活は、体内時計に備わる睡眠のプログラムを円滑に進行する鍵となります。
- 運動の習慣をつける
- 習慣的に運動をしている人は寝付きが良く、深い睡眠が得られる傾向があります。有酸素運動(ウォーキングなど)や適度な筋力トレーニングなどが効果的だとされています。ただし、就寝直前の運動は体を興奮させてしまうので禁物です。
- 就寝の2~3時間前に入浴する
- 深い睡眠のためには寝る前の入浴が良いとされています。入浴で手足の末梢血管からの放熱が促進され、深部体温が低下することで、眠りにつきやすくなる効果があります。寝る直前ではなく、就寝の2~3時間前に少しぬるめのお湯につかることをおすすめします。
- 就寝前のリラックスを心がける
- スムーズに入眠するためには脳の興奮を鎮める必要があります。睡眠の1時間前からはパソコンやスマートフォン、テレビなどの使用を控え、部屋の照明を少し暗くします。呼吸法やアロマテラピーなど、自分なりのリラックス法を見つけると良いでしょう。
- 寝室の環境を整える
- 夏や冬はエアコンなどで快適な温度・湿度を保ちましょう。寝室には、体内時計への影響が強いブルーライトを発するスマートフォンやタブレットの持ち込みを控えます。できるだけ暗くして寝ることが快眠につながります。また、外からの音や光が気になる場合は、防音・遮光カーテンにして寝床の位置を窓から離すなどの工夫をしてみましょう。
- カフェイン、飲酒、喫煙に気を付ける
-
カフェインの摂取量は1日400mg(目安としてはコーヒー700cc程度)を超えると、夜眠りにくくなる可能性があるとされています。特に夕方以降の摂取は影響が出やすいため、カフェインの入った飲料や食品は午後早めまでに取るようにしましょう。
お酒は寝付きを良くしますが、逆に睡眠後半の眠りの質を悪化させ、中途覚醒の回数を増やします。閉塞性睡眠時無呼吸などの睡眠障害の原因にもなります。お酒には依存性があるため適量にとどめ、寝付きを良くする目的の寝酒は控えましょう。
たばこに含まれるニコチンは寝付きを悪くし、中途覚醒など眠りの質を低下させます。睡眠の質を上げるためには、喫煙することが必要です。
まとめ
「睡眠時間は足りているはずなのにスッキリしない」「夜中に何度も目が覚める」など睡眠の悩みがある場合、睡眠の量ではなく質が低下している可能性があります。運動不足やカフェインの取り過ぎなど生活習慣が原因の場合は、ご紹介した睡眠の質を高める方法を試してみてください。ただし、閉塞性睡眠時無呼吸などの病気が隠れている場合もあります。改善しない場合は医療機関の受診をおすすめします。
この記事は『健康づくりのための睡眠ガイド 2023』健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会(厚生労働省)(外部サイトへのリンク)の情報をもとに当社が一部編集・加工して紹介しています。
- 2024/08/07新規作成

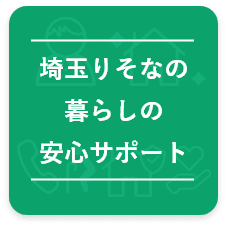
健康
 エアコンを正しく使って賢く節電しよう!日々の工夫で効果的に節約する方法を徹底解説
2025.06.17
エアコンを正しく使って賢く節電しよう!日々の工夫で効果的に節約する方法を徹底解説
2025.06.17
 原因不明の体調不良、それってクーラー病かも?特徴と対策を徹底解説!
2025.06.17
原因不明の体調不良、それってクーラー病かも?特徴と対策を徹底解説!
2025.06.17
 猛暑に備えよう!熱中症の症状と予防法を徹底解説
2025.06.17
猛暑に備えよう!熱中症の症状と予防法を徹底解説
2025.06.17
 花粉で肌荒れが起こることはある? 症状や原因、予防法を紹介
2025.01.17
花粉で肌荒れが起こることはある? 症状や原因、予防法を紹介
2025.01.17
 マインドフルネスとは?ストレス軽減に役立つ?意味や効果、瞑想法を解説
2024.08.07
マインドフルネスとは?ストレス軽減に役立つ?意味や効果、瞑想法を解説
2024.08.07
 睡眠の質を上げるには?質が下がる原因や良い睡眠を取るための方法を紹介
2024.08.07
睡眠の質を上げるには?質が下がる原因や良い睡眠を取るための方法を紹介
2024.08.07
 腸活とは?善玉菌を増やす食材や生活習慣の改善で健康生活を始めよう
2024.08.07
腸活とは?善玉菌を増やす食材や生活習慣の改善で健康生活を始めよう
2024.08.07
 これって更年期障害?女性によくある症状や年齢、原因&対処法を解説
2024.03.21
これって更年期障害?女性によくある症状や年齢、原因&対処法を解説
2024.03.21
 地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~認知症本人編
2024.02.08
地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~認知症本人編
2024.02.08
 地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~にんちしょうって何?
2024.02.08
地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~にんちしょうって何?
2024.02.08
 地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~認知症対応編
2024.02.08
地域包括ケア漫画~みんないつかは年をとる~認知症対応編
2024.02.08
 高齢者の「フレイル」をどう予防する?元気に暮らすためのヒント集!
2023.08.10
高齢者の「フレイル」をどう予防する?元気に暮らすためのヒント集!
2023.08.10
 ロコモとは?要介護を防ぎ健康寿命を延ばすための基礎知識と予防法
2023.08.10
ロコモとは?要介護を防ぎ健康寿命を延ばすための基礎知識と予防法
2023.08.10
 認知症予防に効果的な食事方法や食べ物などを徹底解説
2023.03.01
認知症予防に効果的な食事方法や食べ物などを徹底解説
2023.03.01
 認知症予防に効果的なトレーニングとは?おすすめの運動や脳トレ、長く続けるためのポイントを紹介
2023.03.01
認知症予防に効果的なトレーニングとは?おすすめの運動や脳トレ、長く続けるためのポイントを紹介
2023.03.01
 認知症ケアで大切なことって何?家族が知っておきたい介護のポイントを紹介
2023.03.01
認知症ケアで大切なことって何?家族が知っておきたい介護のポイントを紹介
2023.03.01
 認知症予防にゲームがいいのはなぜ?おすすめの脳トレや気軽にできるゲームを紹介
2023.03.01
認知症予防にゲームがいいのはなぜ?おすすめの脳トレや気軽にできるゲームを紹介
2023.03.01