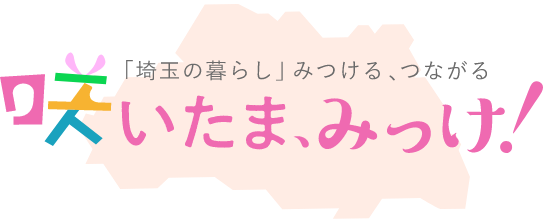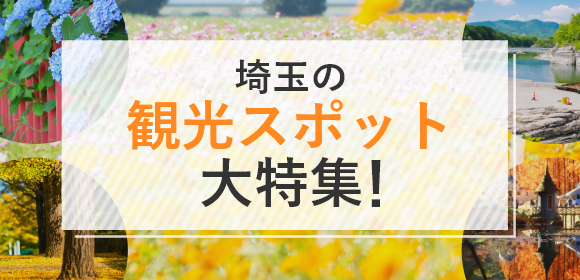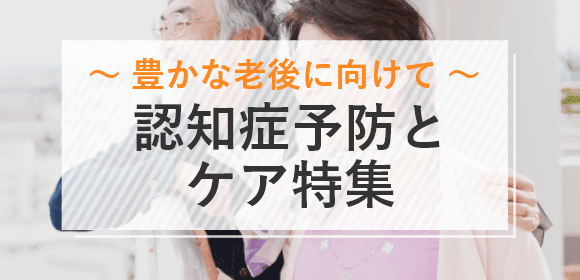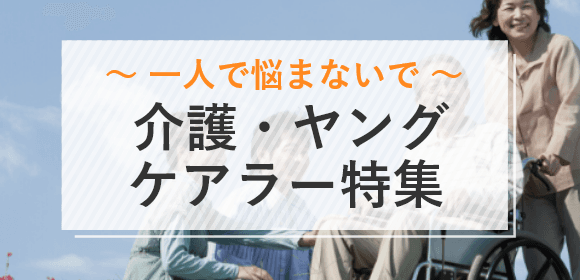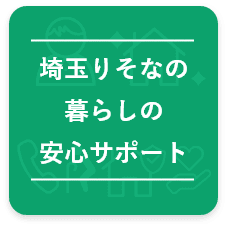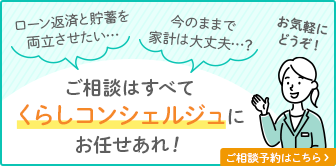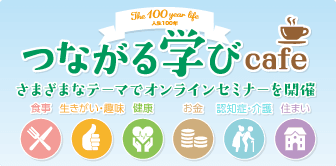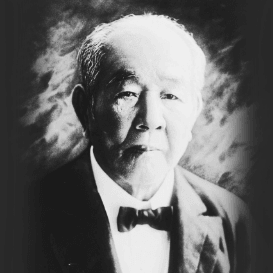
INDEX

監修者プロフィール
金子 賢司 /
CFP
定年後はどう過ごす?考えられる4つの過ごし方
定年後(セカンドライフ)の過ごし方には、どのようなものがあるのでしょうか。4つの過ごし方を見ていきましょう。
趣味を楽しむ
生活を豊かにするうえで、趣味は重要な役割を持っています。
趣味にはストレスを発散できる、交友関係を広げられるなどのメリットがあり、趣味を持ち続けることで自己実現につながるかもしれません。
仕事を辞めて余暇がうまれる定年後なら、これまで時間がなくてできなかったことや、やってみたかったこと、自分の好きなことを十分に楽しめます。
スポーツ・アウトドア・映画鑑賞・写真・音楽・観劇など、趣味の種類はさまざまです。定年を契機に、新しい趣味を見つけるのも良いかもしれません。
旅行する
定年後は仕事がない分、スケジュール調整がしやすいため、旅行に行きやすい環境が整っています。平日の旅行やオフシーズンの旅行もしやすく、遠方へ長期間旅行することも可能です。
急な旅程の変更にも対応でき、気分次第でどこへでも行けるのは、定年後の旅行ならではのメリットだといえるでしょう。
仕事を続ける
定年後、同じ会社で再就職し、仕事を続ける選択肢もあります。
これまでのキャリアを活かせるため、定年前とは違った視点で仕事に取り組めるかもしれません。仕事を通して会社で役割を得られるだけでなく、収入も増やせるため、再就職は仕事にやりがいを感じていた方におすすめです。
仕事を続ける方法には、定年前に勤めていたところと別の会社へ就職する、別業種での仕事をはじめる、起業にチャレンジするなどが考えられます。
より自由な働き方を選択できる定年後だからこそ、仕事を続けることも楽しみの一つとなるのです。
ボランティア活動に取り組む
定年後にボランティア活動に取り組み、社会貢献するのもおすすめです。
仕事がなくなると家にこもりがちになってしまいますが、ボランティアに取り組めば、外出の機会ができ、地域とのつながりができます。
活動の内容次第では運動不足の解消にもなるため、心身の健康を保ちたい方は、ぜひボランティア活動に取り組んでみてください。
定年後に豊かに過ごすために!今からやっておきたいこと
定年後を豊かに過ごすためには、定年前からの準備が欠かせません。定年後に向けて、今からやっておきたいことを3つ紹介します。
1.資金計画を立てる
100歳の人口が増えている現代では、寿命・健康寿命ともに延伸しています。そのため、心身の寿命に合わせて「お金の寿命」も延ばさなければなりません。
定年後は収入が大幅に減ります。収入が限られるなかで長い老後を豊かに過ごすためにも、資金計画を早めに立てて、生活費を確保しておきましょう。
資金計画はできるだけ早めに立てることが大事です。定年後に必要な生活費や、老後資金確保に使える制度は、次の見出しで詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
2.健康に気を付ける
健康でなければ定年後に病気などで動けず、思ったとおりのことができなくなってしまうかもしれません。医療費がかさみ、自分の好きなことにお金を使えなくなってしまう可能性もあります。
定年後の心身の健康は、それまでの生活習慣に大きく左右されます。食事・睡眠・運動を意識し、定期的に健康診断や検診を受け、健康に気を付けて過ごしましょう。
3.定年後にやりたいことの準備を少しずつはじめる
定年後どのように過ごすのかを考えておくと、その過ごし方を実現させるための準備がスムーズにできます。
例えば、定年後に旅行に行きたいなら、旅行先の情報を集めて旅行計画を立てましょう。旅行に最適な時期や必要な資金がわかっていると、定年後すぐに旅行へ行けます。
また、定年後にピアノを趣味にしたいなら、ピアノ教室を調べる、ピアノを練習できる環境を整えるなどしてみてください。
今の職場や家庭以外で、新たなコミュニティを探すのもおすすめです。趣味のサークル、地域のボランティア団体、働いてみたかった仕事で職場を探すなどして、定年後にも参加できるコミュニティを見つけておきましょう。
知っておきたい定年後に必要な生活費
資金計画を立てるうえで知っておきたいのが、定年後の生活費です。定年後の収支の変化と、必要となる生活費について見ていきます。
定年後の収入と支出はどう変わる?
定年後に働かない場合は、給与がなくなり、収入は退職金や年金などしかありません。収入が大幅に減る点は、定年前後の生活の大きな変化といえます。
支出面では、生活費・医療費・介護費などにお金がかかります。場合によっては定年後に住宅ローンや教育費の支払いが必要なこともあり、人によって支出には大きな差があるでしょう。
定年後に仕事を続けるかどうか決め、各種ローンの支払い状況はどうなっているかなどを知っておくと、収支を把握しやすくなります。
定年までにどれくらいの資金を用意しておくべきかを知るためにも、収支の変化を把握しておくことが大事です。
老後に必要な生活費の目安
老後にはどれくらいの生活費が必要なのでしょうか。夫婦2人で過ごす場合の、老後の生活費の目安を見ていきましょう。
生命保険文化センター「令和元年度生活保障に関する調査」によると、夫婦2人の老後最低日常生活費は月額22.1万円、ゆとりある老後生活費は月額36.1万円となっています。
また、総務省「令和2年家計調査(家計収支編)」によると、世帯主の年齢階級が65歳以上の場合の1ヵ月の消費支出は24万1,724円です。
上記2つの調査結果から、夫婦2人で過ごす場合、最低生活費は265.2万円/年、平均生活費は290.1万円/年、ゆとりのある生活費は433.2万円/年が目安です。
ただし、生活状況によって生活費は大きく変わるため、目安より生活費が少なくなる場合もあれば、生活費がより必要になる場合もあるでしょう。
どのような生活がしたいかを考えて、これらの調査結果などを参考に必要な生活費を用意しておいてください。
定年後の生活費はどう準備すれば良い?
定年後の生活費を準備するには、どのような方法があるのでしょうか。生活資金の支えとなる年金と、今からでも取り組める資産運用について解説します。
自分が将来貰える年金額を把握する
年金制度は、定年後の生活を支える重要な仕組みです。年金制度は国民年金と厚生年金の2階建てで、国民年金は加入月数に応じて、厚生年金は報酬額や加入期間に応じて年金を受給できます。
自分が将来貰える年金額の目安は、誕生月に毎年送られてくる「ねんきん定期便」で確認可能です。
また、日本年金機構の「ねんきんネット」を使えば、パソコンやスマートフォンから年金情報を確認できるため、チェックしてみましょう。
年金を増額して受け取る
年金の受給開始は原則65歳からですが、受け取り時期を遅らせる(繰り下げる)ことで給付額を増やせます。
増額は繰り下げた月数×0.7%で計算され、繰り下げ上限である75歳まで繰り下げると、年金受給額は最大84%増額されます。
増額の効果は生涯続くため、可能な限り繰り下げておくと定年後の生活費確保に役立ちます。ただし、繰り下げ期間中は年金を受給できません。繰り下げ期間の生活費を確保できるかどうかについて確認したうえで、慎重に検討してください。
また、年金の受給時期を早める(繰り上げる)こともできますが、繰り上げた場合は繰り上げ月数に応じて年金受給額が減額されます。減額を承知のうえで早く年金を受給したい場合は、繰り上げを検討してみましょう。
資産運用する
定年後の生活費を貯めるために、こつこつと貯金するのもおすすめです。毎月少しずつでも貯金しておけば、定年後までにまとまった金額を貯められます。
ただし、昨今の預金金利は低く、ただ資金を銀行に預けているだけでは、それ以上の資金は得られません。
より効率良く資金を貯めたいなら、資産運用がおすすめです。資産運用には投資信託や株式投資、債券投資などがあります。
- 投資信託:投資家から集めた資金をもとに、投資の専門家が運用する方法
- 株式投資:企業が発行する株式を買い、配当金や売買差益を得る方法
- 債券投資:国や自治体が発行する債券を買い、利息と償還金を得る方法
- iDeCo:税制上の優遇を受けられる私的年金制度
- NISA:投資信託の運用にあたって税制上の優遇措置を受けられる制度。制度利用の年齢制限が18歳以上であるため、定年後でも利用できる
投資にはリスクとリターンがあり、種類によって特徴が異なるため、それぞれの特徴を理解したうえで資産運用することが重要です。
まとめ
自分の時間をたくさんとれる定年後は、趣味を楽しんだり、旅行に出かけたりするなど、余暇を活かしてさまざまなことに取り組めます。定年後の選択肢を広げるためにも、資金計画と併せて定年後にしたいことを早い段階から考えておきましょう。
資金計画を立てる際は、定年後の収支の変化を知っておく必要があります。今回紹介した生活費の目安も参考にしながら、目指す定年後の暮らしにどのような準備が必要かを考えてみてください。
定年後の生活費を確保するには、できるだけ早めに準備をはじめることがおすすめです。iDeCoやNISAなど、非課税制度も有効活用しながら、より効率的に資金を確保できるよう工夫しましょう。
お金のこと
 ファイナンシャル・ウェルビーイングとは何か?メリットと実現方法
2025.05.26
ファイナンシャル・ウェルビーイングとは何か?メリットと実現方法
2025.05.26
 2025年(令和7年)分の確定申告はいつからいつまで?期限内に申告できなかった場合のペナルティなども解説
2026.01.15
2025年(令和7年)分の確定申告はいつからいつまで?期限内に申告できなかった場合のペナルティなども解説
2026.01.15
 お年玉は何歳まであげるべき?年齢別の相場やマナー、キャッシュレス対応について紹介
2024.12.11
お年玉は何歳まであげるべき?年齢別の相場やマナー、キャッシュレス対応について紹介
2024.12.11
 児童手当と児童扶養手当の違いは? シングルマザーがもらえる 手当について解説
2024.07.26
児童手当と児童扶養手当の違いは? シングルマザーがもらえる 手当について解説
2024.07.26
 「お盆玉」今年はどうする? 金額の目安や渡し方について解説
2024.07.26
「お盆玉」今年はどうする? 金額の目安や渡し方について解説
2024.07.26
 紙幣の変更はいつから?肖像に選ばれた人物や紙幣の歴史、新札の疑問について解説
2024.03.21
紙幣の変更はいつから?肖像に選ばれた人物や紙幣の歴史、新札の疑問について解説
2024.03.21
 遺言書の書き方とは?自分で書く方法や注意点も解説
2023.12.26
遺言書の書き方とは?自分で書く方法や注意点も解説
2023.12.26
 なぜ今「金融教育」?必要な理由や学習内容を解説
2023.08.25
なぜ今「金融教育」?必要な理由や学習内容を解説
2023.08.25
 豊かなセカンドライフに向けて ~50代から考えるライフプラン~
2023.07.20
豊かなセカンドライフに向けて ~50代から考えるライフプラン~
2023.07.20
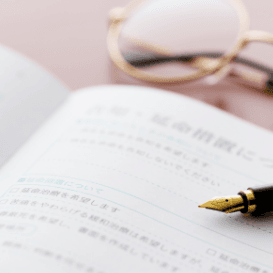 よりよく人生を終えるために「エンディングノート」はどう書いたらいい?
2023.07.20
よりよく人生を終えるために「エンディングノート」はどう書いたらいい?
2023.07.20
 サイドFIREとは?FIREとの違い、メリット・デメリットなどを詳しく解説
2023.04.05
サイドFIREとは?FIREとの違い、メリット・デメリットなどを詳しく解説
2023.04.05
 定年後の過ごし方を充実させるには?定年後に向けた資金準備方法も解説
2023.03.01
定年後の過ごし方を充実させるには?定年後に向けた資金準備方法も解説
2023.03.01
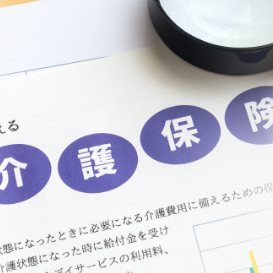 介護保険とは? 制度のしくみや利用できるサービスなどを分かりやすく解説
2023.03.01
介護保険とは? 制度のしくみや利用できるサービスなどを分かりやすく解説
2023.03.01