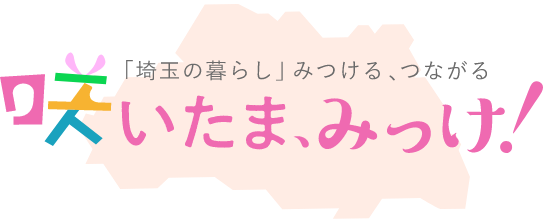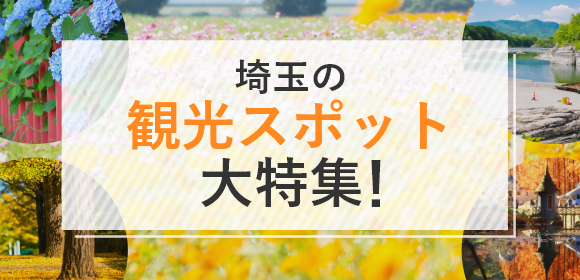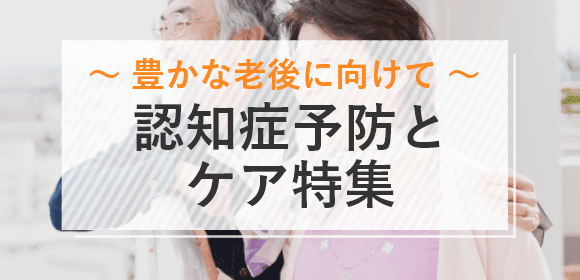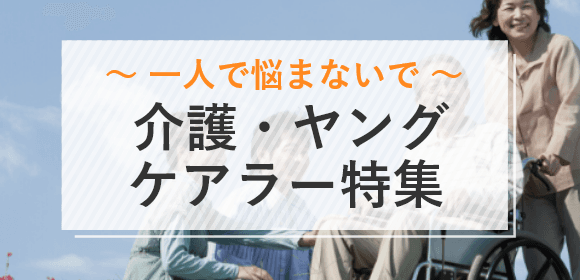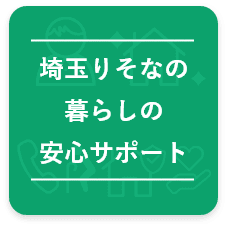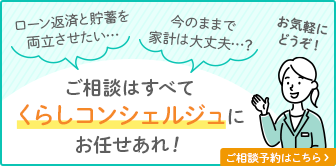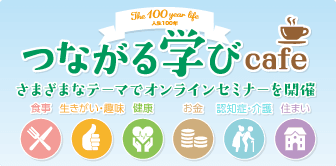2025年(令和7年)分の確定申告はいつからいつまで?
期限内に申告できなかった場合のペナルティなども解説

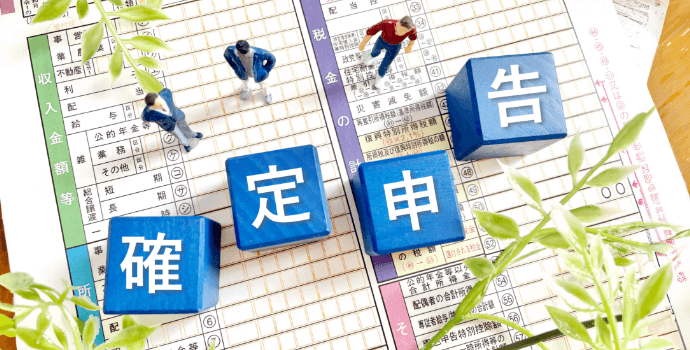
確定申告は、所得に基づいて税額を確定し、必要に応じて納税や還付を行う手続きです。フリーランスや個人事業主だけでなく、副業で20万円以上の収入がある会社員なども確定申告を行う必要があります。2025年(令和7年)分の確定申告について、具体的な日程や申告が遅れた場合のペナルティ、期限内に納税できない場合の段取りなどについて解説します。

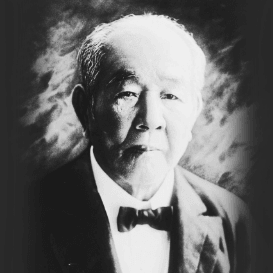
INDEX
確定申告の申告期限は?
まず、2025年(令和7年)分の確定申告書の受付期間(確定申告期間)について確認しておきましょう。
【2026年(令和8年)2月16日(月)~3月16日(月)】
なお、払い過ぎた税金の還付を受けるための還付申告は2026年(令和8年)1月1日(木)から行えます。還付申告については次の章でご説明します。
そもそも確定申告とは?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入と支出の金額に基づいて、所得税額を計算して確定させる手続きのことです。納税額を事前に概算する予定納税を行っている場合は、納税額の過不足を確定させる手続きとなります。
なぜ確定申告の必要があるのでしょうか?それは、日本の所得税の納税は「申告納税制度」になっているからです。申告納税制度では、納税者自身が税額の計算から納税までを行わなければなりません。年末調整を行う会社員や、一定の収入以下で確定申告の義務がない場合を除いて、収入を得ている人は所得に応じた所得税を納める必要があります。
ただし、年末調整を行っている会社員でも、確定申告をした方が所得税の還付を受けられて得をすることがあります(還付申告)。還付申告を行う主なケースを以下に挙げます。
- 【還付申告を行う場合】
-
- 年末調整時に生命保険料控除を行わなかった
- 住宅ローンを払った(初年度のみ。2年目以降は年末調整で行う)
- 多額の医療費がかかった
- ふるさと納税で6自治体以上に寄付した(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できない)
- 災害や盗難により住宅や家財に損害を受けたなど
還付申告は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間申告できます。
確定申告の期限を過ぎたらどうなる?
確定申告は、提出期限を過ぎても受け付けてもらえます。しかし、「期限後申告」となることで、次のようなペナルティが課せられてしまいます。
無申告加算税
本来の納税額に「無申告加算税」が上乗せされます。また、税務署からの事前通知の前か後か、税務署の調査を受ける前の申告なのか、調査後の申告なのかによって、税率が異なります。
- 無申告加算税の税率
-
- ①税務署からの調査の事前通知の前に、自主的に期限後申告した場合:5%
- ②税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告した場合:10%
- ※ただし、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、納付すべき税金が、50万円までの部分は10%、50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%の割合になります。
- ③税務署からの調査を受けた後に期限後申告した場合:15%
- ※ただし、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、納付すべき税金が、50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%の割合になります。
一方で、次の要件を全て満たしている場合は「期限内申告を行う意思はあった」と認められ、無申告加算税は課されません。そのため、期限内に確定申告を忘れた場合でも、その事実を把握した際には、できるだけ早く申告するようにしましょう。
- 無申告加算税がかからない要件
-
- 申告期限後、1か月以内に自主的に申告している
- 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する
無申告加算税に関する詳細は、国税庁ホームページ「確定申告を忘れたとき」をご覧ください。
確定申告を忘れたとき|国税庁(外部サイトへのリンク)
延滞税
納税が遅れた日数分に応じて「延滞税」が加算されます。最高税率は原則として年14.6%です。詳しい計算方法は、国税庁のウェブサイトで計算方法を確認できます。
延滞税の計算方法|国税庁(外部サイトへのリンク)
青色申告特別控除が受けられなくなる
青色申告では最大65万円(e-Taxを利用しない場合等は55万円)の青色申告特別控除が受けられますが、提出期限に遅れると高額の控除要件を満たさなくなり、最大10万円の控除となります。
青色申告の承認が取り消しになる
法人の場合、2事業年度連続で期限内に確定申告書を提出しなかった場合、青色申告者としての承認が取り消されます。また、個人事業主でも、帳簿不備や不正などにより青色申告の承認が取り消されることがあります。
期限までに納税できない
ときはどうする?
確定申告期間内の納税が遅れそうな場合には、以下の二つの制度が使えることがあります。
猶予制度
災害で財産を損失したり、病気をしたりなど特定の事情がある場合は「国税の猶予制度」を使えることがあります。原則として1年以内の期間に限ります。
猶予期間中の延滞税が軽減されるなどのメリットもありますから、要件に当てはまる場合は所轄の税務署に相談しましょう。
納税に関する総合案内|国税庁(外部サイトへのリンク)
延納制度
納付期間内までに納付税額の2分の1以上を納付することで、残りの税額の納付を5月31日まで延長できるという制度です。ただし、延納期間中は利子税がかかります。
制度を利用する場合は、確定申告書第一表の「延納の届出」欄の「申告期限までに納付する金額」と「延納届出額」に、それぞれ希望する金額を記載します。
確定申告後の訂正は
できる?
確定申告では、期間内の最後に提出した確定申告書がその年の申告書として扱われることになります。もし、提出期間内に間違いに気付いたら、訂正した申告書を提出すれば問題ありません。
提出期限を過ぎてしまった場合、税額が多かったか少なかったかに応じて、異なる手続きが必要です。税額を実際の金額より多く申告していた場合は「更正の請求書」を行い、払い過ぎた税金の還付を受けます。税額を実際の金額より少なく申告していた場合は「修正申告」を行い、不足分を追加で納付します。
「更正の請求書」は申告期限から5年以内なら提出できます。
一方、修正申告では原則として「過少申告加算税」が課される可能性があります。ただし、税務署からの調査の事前通知前に自主的に行えば、過少申告加算税はかかりません。
まとめ
令和7年(2025年)分の確定申告は、2月16日から3月16日までの期間で行われます。確定申告が必要な場合には、事前に必要な書類をそろえ、収入や所得、控除の額を把握することが大切です。なお、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を活用することで、時間や手間を大幅に節約できるほか、還付金がある場合の受け取りも早くなります。
早めの準備を心がけて、期間内に申告を済ませましょう。
お金のこと
 ファイナンシャル・ウェルビーイングとは何か?メリットと実現方法
2025.05.26
ファイナンシャル・ウェルビーイングとは何か?メリットと実現方法
2025.05.26
 2025年(令和7年)分の確定申告はいつからいつまで?期限内に申告できなかった場合のペナルティなども解説
2026.01.15
2025年(令和7年)分の確定申告はいつからいつまで?期限内に申告できなかった場合のペナルティなども解説
2026.01.15
 お年玉は何歳まであげるべき?年齢別の相場やマナー、キャッシュレス対応について紹介
2024.12.11
お年玉は何歳まであげるべき?年齢別の相場やマナー、キャッシュレス対応について紹介
2024.12.11
 児童手当と児童扶養手当の違いは? シングルマザーがもらえる 手当について解説
2024.07.26
児童手当と児童扶養手当の違いは? シングルマザーがもらえる 手当について解説
2024.07.26
 「お盆玉」今年はどうする? 金額の目安や渡し方について解説
2024.07.26
「お盆玉」今年はどうする? 金額の目安や渡し方について解説
2024.07.26
 紙幣の変更はいつから?肖像に選ばれた人物や紙幣の歴史、新札の疑問について解説
2024.03.21
紙幣の変更はいつから?肖像に選ばれた人物や紙幣の歴史、新札の疑問について解説
2024.03.21
 遺言書の書き方とは?自分で書く方法や注意点も解説
2023.12.26
遺言書の書き方とは?自分で書く方法や注意点も解説
2023.12.26
 なぜ今「金融教育」?必要な理由や学習内容を解説
2023.08.25
なぜ今「金融教育」?必要な理由や学習内容を解説
2023.08.25
 豊かなセカンドライフに向けて ~50代から考えるライフプラン~
2023.07.20
豊かなセカンドライフに向けて ~50代から考えるライフプラン~
2023.07.20
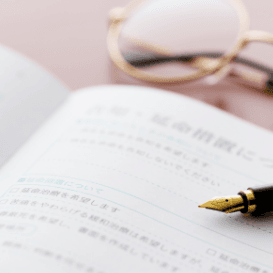 よりよく人生を終えるために「エンディングノート」はどう書いたらいい?
2023.07.20
よりよく人生を終えるために「エンディングノート」はどう書いたらいい?
2023.07.20
 サイドFIREとは?FIREとの違い、メリット・デメリットなどを詳しく解説
2023.04.05
サイドFIREとは?FIREとの違い、メリット・デメリットなどを詳しく解説
2023.04.05
 定年後の過ごし方を充実させるには?定年後に向けた資金準備方法も解説
2023.03.01
定年後の過ごし方を充実させるには?定年後に向けた資金準備方法も解説
2023.03.01
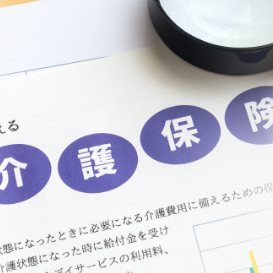 介護保険とは? 制度のしくみや利用できるサービスなどを分かりやすく解説
2023.03.01
介護保険とは? 制度のしくみや利用できるサービスなどを分かりやすく解説
2023.03.01