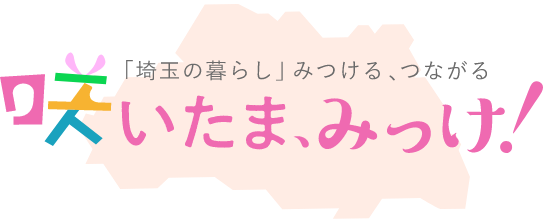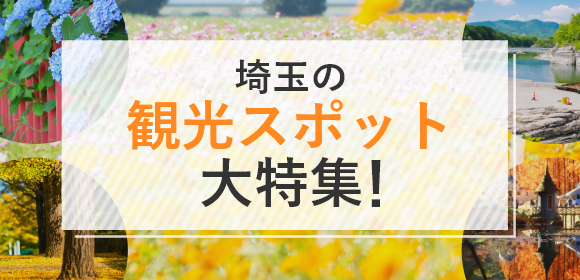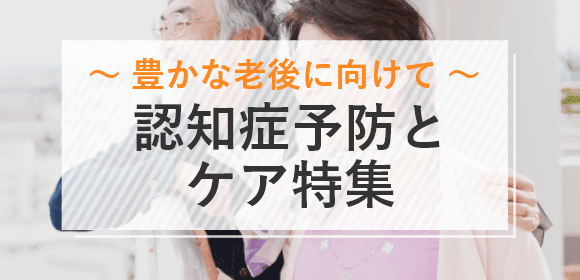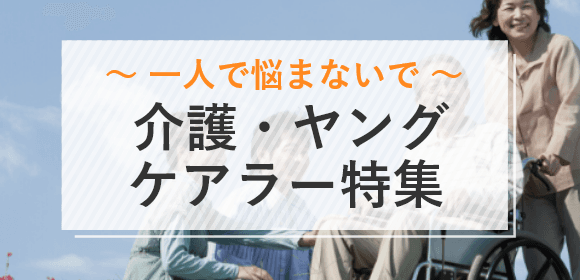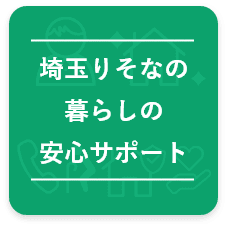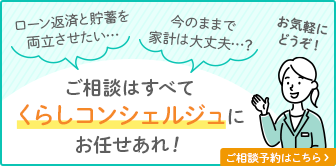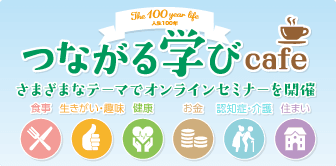豊かなセカンドライフに向けて ~50代から考えるライフプラン~


20代の頃は夢のまた夢に思えた老後の人生。しかし50代ともなると、それがはっきりと肌で感じられるようになります。退職後はどう過ごそうかと想像することも多くなるかわりに、老後の生活費について真剣に悩み始めるようにもなるのが50代です。
本稿では、50代の人が第二の人生を歩むにあたり、どのようなライフプランで臨めば良いかについてお伝えします。

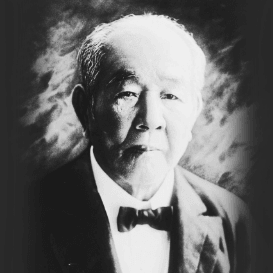
INDEX
今後のライフイベントから逆算する
退職後のライフプランを考えるにあたり、まずは収入と支出について把握する必要があります。しかし退職前と退職後では、収入の形も額も大きく変わります。そこで、収入と支出を以下のように分けると状況を把握しやすくなります。
①退職前の収入 ②退職前の支出 ③退職後の収入 ④退職後の支出
このように切り分けてみると、生活がガラリと変わるイメージも湧くはずです。
①退職前の収入
これは最も把握しやすいものです。現在の収入をベースに、何歳までそれが続くかについて予想しておきましょう。また退職金の額も把握しておかなければなりません。
②退職前の支出
これも現状から導き出しやすいものです。生活費のほか、教育や住宅を含む各種ローン、保険など、支出がどれくらいあるかを並べて把握しておきましょう。これに伴い、保険の見直しなど、すぐに削減できそうな支出も見えてくるはずです。また、退職前の支出に関しても、収入と同じようにいつまでそれが続くのかも予想しておかねばなりません。金銭的に多少余裕があるのであれば、住宅ローンなどは繰り上げ返済をしてしまうほうが、後々の生活が楽になります。
③退職後の収入
退職後の収入でベースとなるのは「公的年金」です。50歳以上の人を対象に、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」の中には、現在と同じ加入条件で60歳まで継続して加入したと仮定して計算された「老齢年金の見込額」が記載されています。その金額を収入のベースとして考え、退職時の資産残高やその他の収入を考慮してセカンドライフの資金計画を立てていきましょう。
④退職後の支出
退職後の支出については、まず日々の生活費が挙げられます。退職後の生活費は退職前と比べて、同額から2割程度は多めに見積もっておくのが一般的です。その理由として以下の3点が挙げられます。
・現在の生活水準の維持
退職後、収入に合わせて生活水準を引き下げることは、精神的にも現実的にも実は非常に難しいものです。このため、基本的には現在と同額の支出は考えておかねばなりません。
・余暇の充実
退職すると現在よりも自由な時間が圧倒的に増えます。このため、自分の好きなことをやりたい気持ちになるでしょう。それに伴い、当然出費も増えますので、その分は生活費に上乗せすることになります。
・社会情勢
日本銀行は現在、2%の物価安定の目標を掲げています。2%ずつのインフレを目指しているということはつまり、支給される公的年金が現実的には毎年2%ずつ減少していくと考えるべきです。さらに消費税の増税や社会保険料の負担増加なども懸念されます。
資産運用こそが、ゆとりあるセカンドライフの決め手
収入と支出を把握する際「キャッシュフロー表」の作成をおすすめします。キャッシュフロー表とは、老後にいたるまでの大雑把な家計簿のようなものです。家族を含めて、毎年の収入と支出を簡単な表にしていきます。キャッシュフロー表を作成してみると、頭で考えているよりもずっと具体的に将来の生活が予想できるようになるはずです。
そしてここから逆算して、将来的にいくらあれば良いかを考え、資産運用のリターンを組み立てていきます。もちろんリターンにはリスクがつきものです。無理のない堅実な資産運用を念頭に、なるべくゆとりある老後を目指しましょう。
定期的な運用状況の確認を
50代の資産運用は、登山でいうところの7~8合目です。これまでは積極的に資産を運用してきたのであれば、将来的には比較的安定したものに資産に移すことを考える時期が近付いているかもしれません。
リスク志向は人それぞれですが、セカンドライフが始まる時期を一つの区切りとして、あらためて目標を設定、そのうえで商品の選定や組み換えを行うことをおすすめします。そして、退職にいたるまで定期的に運用状況を確認していくことが、豊かなセカンドライフに向けた第一歩といえるでしょう。
※当サイトの記事は執筆時点の税制、関係法令などに基づき記載して製作したものです。
今後税務の取り扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容、数値などは将来にわたって保証されるものではありません。
お金のこと
 ファイナンシャル・ウェルビーイングとは何か?メリットと実現方法
2025.05.26
ファイナンシャル・ウェルビーイングとは何か?メリットと実現方法
2025.05.26
 2025年(令和7年)分の確定申告はいつからいつまで?期限内に申告できなかった場合のペナルティなども解説
2026.01.15
2025年(令和7年)分の確定申告はいつからいつまで?期限内に申告できなかった場合のペナルティなども解説
2026.01.15
 お年玉は何歳まであげるべき?年齢別の相場やマナー、キャッシュレス対応について紹介
2024.12.11
お年玉は何歳まであげるべき?年齢別の相場やマナー、キャッシュレス対応について紹介
2024.12.11
 児童手当と児童扶養手当の違いは? シングルマザーがもらえる 手当について解説
2024.07.26
児童手当と児童扶養手当の違いは? シングルマザーがもらえる 手当について解説
2024.07.26
 「お盆玉」今年はどうする? 金額の目安や渡し方について解説
2024.07.26
「お盆玉」今年はどうする? 金額の目安や渡し方について解説
2024.07.26
 紙幣の変更はいつから?肖像に選ばれた人物や紙幣の歴史、新札の疑問について解説
2024.03.21
紙幣の変更はいつから?肖像に選ばれた人物や紙幣の歴史、新札の疑問について解説
2024.03.21
 遺言書の書き方とは?自分で書く方法や注意点も解説
2023.12.26
遺言書の書き方とは?自分で書く方法や注意点も解説
2023.12.26
 なぜ今「金融教育」?必要な理由や学習内容を解説
2023.08.25
なぜ今「金融教育」?必要な理由や学習内容を解説
2023.08.25
 豊かなセカンドライフに向けて ~50代から考えるライフプラン~
2023.07.20
豊かなセカンドライフに向けて ~50代から考えるライフプラン~
2023.07.20
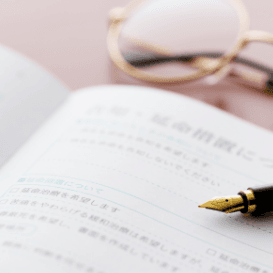 よりよく人生を終えるために「エンディングノート」はどう書いたらいい?
2023.07.20
よりよく人生を終えるために「エンディングノート」はどう書いたらいい?
2023.07.20
 サイドFIREとは?FIREとの違い、メリット・デメリットなどを詳しく解説
2023.04.05
サイドFIREとは?FIREとの違い、メリット・デメリットなどを詳しく解説
2023.04.05
 定年後の過ごし方を充実させるには?定年後に向けた資金準備方法も解説
2023.03.01
定年後の過ごし方を充実させるには?定年後に向けた資金準備方法も解説
2023.03.01
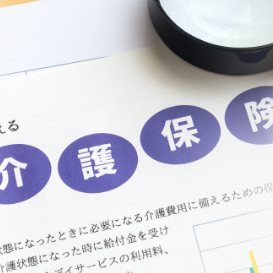 介護保険とは? 制度のしくみや利用できるサービスなどを分かりやすく解説
2023.03.01
介護保険とは? 制度のしくみや利用できるサービスなどを分かりやすく解説
2023.03.01